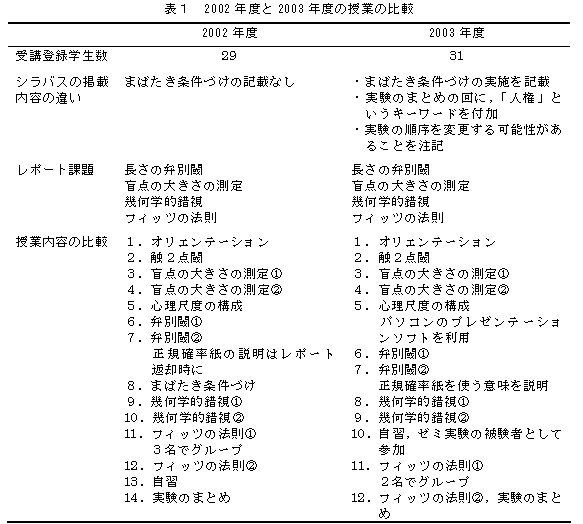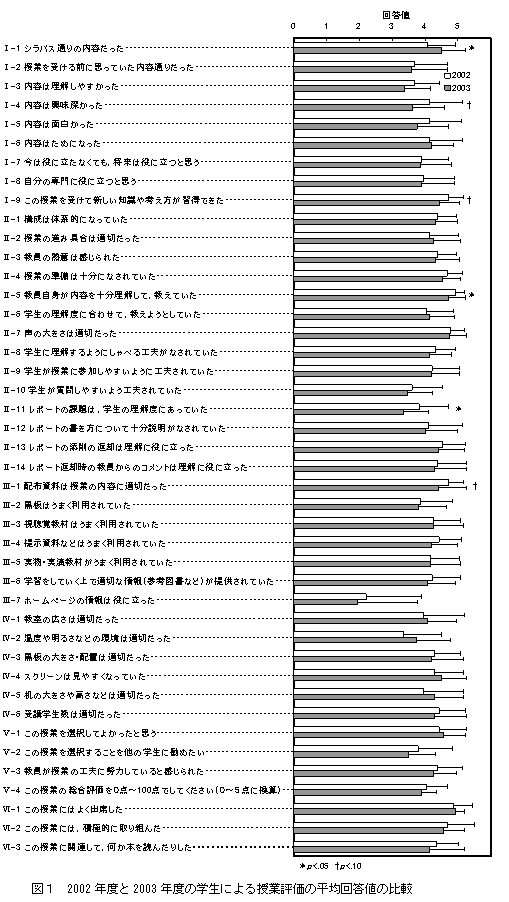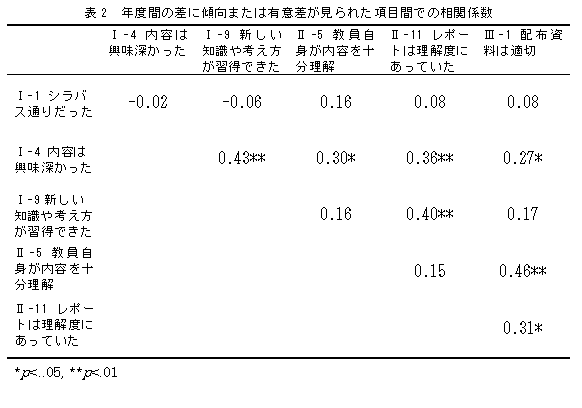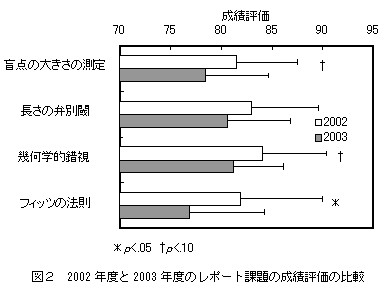Algozzine, B., Beattie, J., Bray, M., Flowers, C., Gretes, J., Howley, L., Mohanty, G. and Spooner, F. 2004 Student Evaluation of College Teaching: A Practice in Search of Principles. College Teaching, 52, 134-141.
Gaski, J.F. 1987 On “Construct Validity of Measurres of College Teaching Effectiveness”. Journal of Educational Psychology, 79, 326-330.
Greenwald, A.G. and Gillmore, G.M. 1997 No pain, No Gain? The Importance of Measuring Course Workload in Student Ratings of Instruction. Journal of Educational Psychology, 89, 743-751.
高等教育情報センター 2003 教員評価制度の導入と大学の活性化 地域科学研究会
栗田真樹・宇田川拓雄 2003 学生による授業評価と満足度測定の問題点. 流通科学大学論集 人間・社会・自然編, 15, 59-72.
Marsh, H. and Roche, L. 2000 Effects of grading leniency and low workload on students' evaluations of teaching : Popular myth, bias, validity, or innocent bystanders? Journal of Educaitonal Psychology, 92, 202-28.
Mason, P., Steagall, J. and Fabritius, M. 1995 Student evaluations of faculty: A new procedure for using aggregate measures of performance, Economics of Education Review, 12 , 403-416.
松尾太加志・近藤倫明・原口雅浩 1995 心理学教育における統合的教育の実践報告. 北九州大学文学部紀要(人間関係学科), 2, 31-42.
三田誠弘 1999 大学はどこに行くのか 安岡高志・滝本喬・三田誠弘・香取草之助・生駒俊明 授業を変えれば大学は変わる プレジデント社, Pp.193-242.
中原龍輝・遠藤誠二・K,ワクター 2004 学生による授業評価に関する日米大学間異同点の一考察――富士常葉大学とThe University of Mississippiとの比較を中心に. 富士常葉大学研究紀要, 4, 157-186.
Sproule, R. 2000 Student Evaluation of Teaching: A Methodological Critique of Conventional Practices.
Education Policy Analysis Archives,
8(50). (
http://epaa.asu.edu/epaa/v8n50.html)
田中あゆみ・藤田哲也 2003 大学生の達成目標と授業評価,学業遂行の関連. 日本教育工学雑誌, 27,397-403.
浦上昌則・林雅代・石田裕久 1999 受講動機別にみた授業評価と満足度. アカデミア 人文・社会科学編(南山大学) , 70,515-540.
宇佐美寛 2004 大学授業の病理 FD批判 東信堂
渡辺勇一 2001 学生による授業評価をどう見るか. 生物科学,52,209-216.