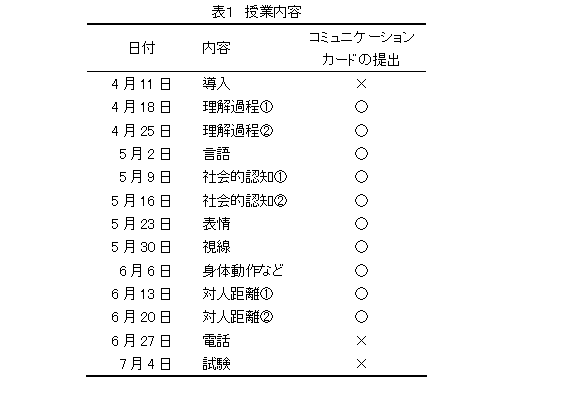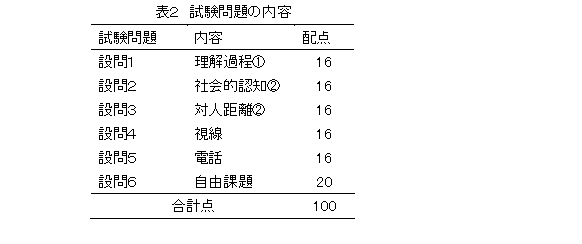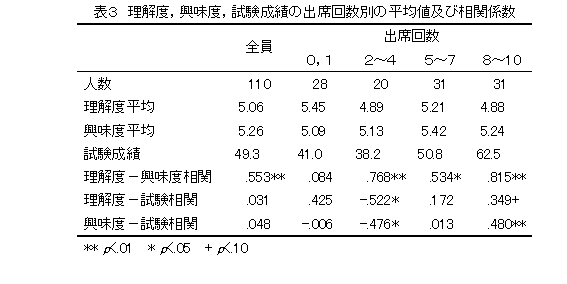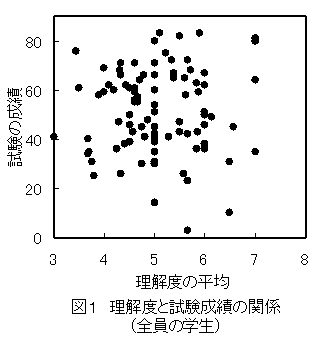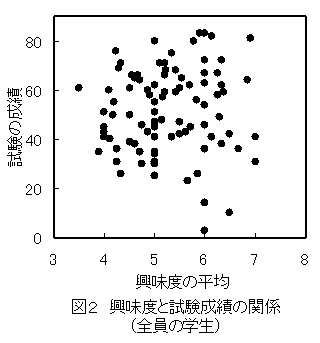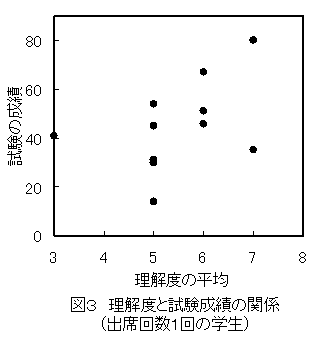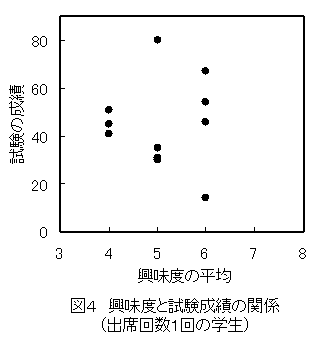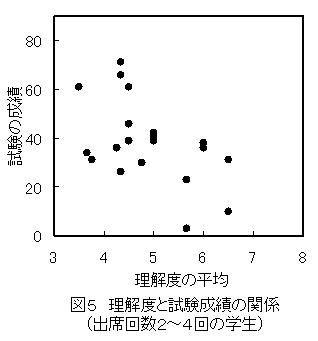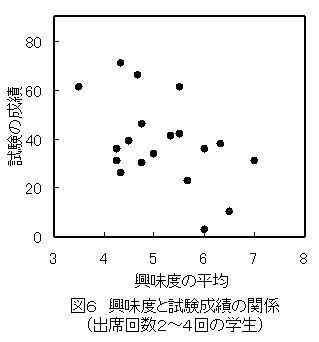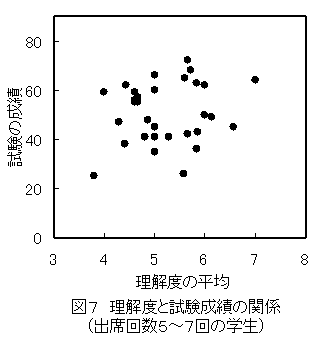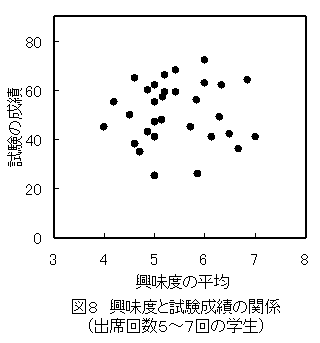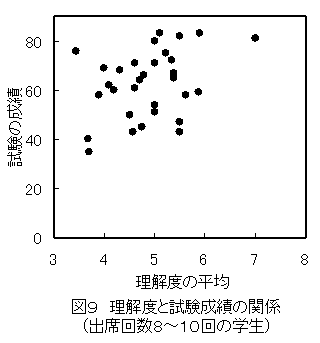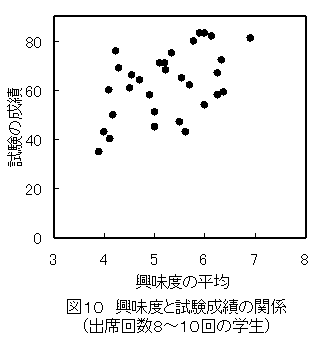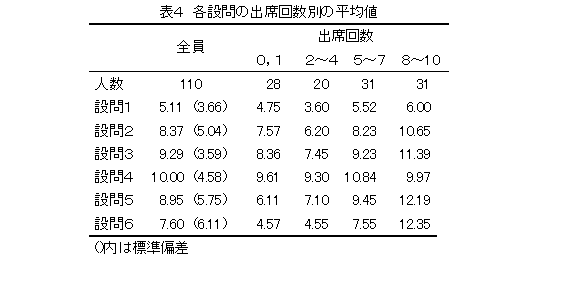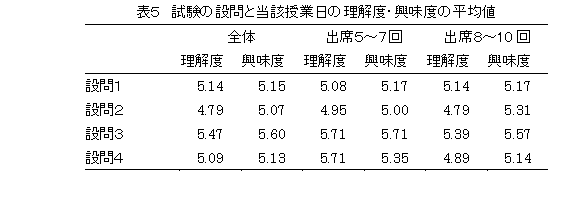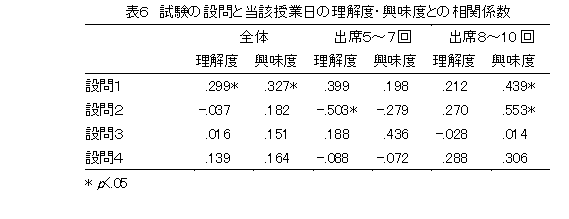Abrami, P.C., d'Apollonia, S., and Cohen, P.A. 1990 Validity of student ratings of instruction: What we know and what we do not. Journal of Educational Psychology, 82, 219-231.
Algozzine, B., Beattie, J., Bray, M., Flowers, C., Gretes, J., Howley, L., Mohanty, G. and Spooner, F. 2004 Student evaluation of college teaching: A practice in search of principles. College Teaching, 52, 134-141.
Bausell, R.B. and Magoon, J. 1972 Expected grade in a course, grade point average, and student ratings of the course and instructor. Educational and Psychological Measurements, 32, 1013-1023.
Brown, D.L. 1976 Faculty ratings and student grades: A university-wide multiple regression analysis. Journal of Educational Psychology, 68, 573-578.
Centra, J. A. 2003 Will teachers receive higher student evaluations by giving higher grades and less course work? Research in Higher Education, 44, 495-518.
Cohen, P.A. 1981 Student ratings of instruction and student achievement: A meta analysis of multisection validity studies. Review of Educational Research, 51, 281-309.
Eiszler, C. F. 2002 College students' evaluations of teaching and grade inflation. Research in Higher Education, 43, 483-501.
Feldman, K.A. 1989 The association between student ratings of specific instructional dimensions and student achievement: Refining and extending the synthesis of data from multisection validity studies. Research in Higher Education, 30, 583-645.
Gaski, J.F. 1987 On "Construct Validity of Measures of College Teaching Effectiveness". Journal of Educational Psychology, 79, 326-330.
Greenwald, A.G. and Gillmore, G.M. 1997 No pain, No Gain? The Importance of Measuring Course Workload in Student Ratings of Instruction. Journal of Educational Psychology, 89, 743-751.
Howard, G.S. and Maxwell, S.E. 1980 The correlation between student satisfaction and grades: A case of mistaken causation? Journal of Educational Psychology, 72, 810-820.
Hoyt, D.P. 1973 Measurement of instructional effectiveness. Research in Higher Education, 1, 367-378.
石浦章一 2005 東大教授の通信簿―「授業評価」から見えてきた東京大学 平凡社
Johnson, R. 2000 The authority of the student evaluation questionnaire. Teaching in Higher Education, 5, 419-434.
Koon, J., and Murray, H.G. 1995 Using multiple outcome to validate student ratings of overall teacher effectiveness. Journal of Higher Education, 66, 61-81.
Marsh, H.W. 1984 Students' evaluations of university teaching: dimensionality, reliability, validity, potential biases, and utility. Journal of Educational Psychology, 76, 707-754.
Marsh, H.W. and Roche, L.A. 1997 Making students' evaluations of teaching effectiveness effective. American Psychologist, 52, 1187-1197.
Marsh, H.W. and Roche, L.A. 2000 Effects of grading leniency and low workload on students' evaluations of teaching : Popular myth, bias, validity, or innocent bystanders? Journal of Educaitonal Psychology, 92, 202-228.
松田文子・三宅幹子・谷村亮・小嶋佳子 1999 学生による授業評価と自己評価,授業選択態度,及び成績の関係−教職必修科目「生徒指導論」の場合−.広島大学教育学紀要第一部(心理学),48,121−130.
McKeachie, W.J. 1997 Student ratings: The validity of use. American Psychologist, 52, 1218-1225.
Nelson, J.P. and Lynch, K.A. 1984 Grade inflation, real income, simultaneity, and teaching evaluations. The Journal of Economic Education, 16, 21-37.
西林克彦 2005 わかったつもり 光文社
Norman, D.A. and Bobrow, D.G. 1975 On data-limited and resource-limited processes. Cognitive Psychology, 7, 44-64.
サックス,P. 後藤将之 (訳) 2000 恐るべきお子さま大学生たち―崩壊するアメリカの大学 草思社(Sacks, P. 1996 Generation X Goes to College: An Eye-Opening Account of Teaching in Postmodern America. Open Court Publishing Company.)
Sproule, R. 2000 Student evaluation of teaching: A methodological critique of conventional practices.
Education Policy Analysis Archives,
8 .
Available at:
http://epaa.asu.edu/epaa/v8n50.html
田中あゆみ・藤田哲也 2003 大学生の達成目標と授業評価,学業遂行の関連. 日本教育工学雑誌, 27,397-403.
宇佐美寛 2004 大学授業の病理 東信堂
安岡高志・吉川政夫・高野二郎・峯崎俊哉・成嶋弘・光澤舜明・道下忠行・香取草之助 1989 学生による講義評価−成績と講義評価の関係について−.一般教育学会誌,11,99−102.